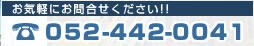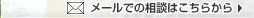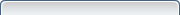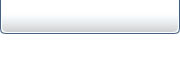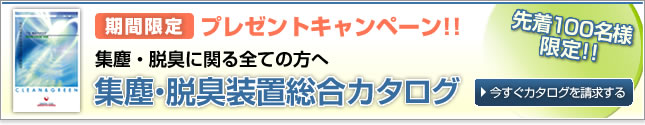[1] 集塵機 選定のポイント |
[2] フード設置上の原則 |
| 1 計画のステップ |
1) 発塵個所、発塵方向、粉塵の性質などの発塵源の把握 2) 大気汚染防止法等関連法規、特に公害関係条例、労働衛生関係法規との関連を調査 3) 制御方法の選定と計画 4) 集塵方法と後処理方法の決定 5) 集塵機の設置場所とダクトフードの決定 6) 各部の性能計算・・・・排風機、電動機の選定 |
| 2 集塵方法を選ぶ |
対象粉塵によって集塵方式を選ぶ対象粉塵を十分に検討せず集塵機を選定すると、設置後さまざまな問題が生じます。その結果、 解決のために多くの時間と費用がかかってしまいます。それゆえ、対象粉塵についてよく調べてから、集塵機を選ぶことが大切になります。 対象粉塵の性状1.粒度分布・比重2.安息角・粘燃性 3.温度 4.化学的性質 (親水性・撥水性・腐食性・爆発性・その他) |
| 3 後処理方法を選ぶ |
集めた粉塵の後処理方法を決める発生粉塵は空気中に浮遊しているので、その発生量を予測しづらいです。集塵機を設置後、捕集量が多いケースがあります。 そのため、補集した粉塵の後処理をどうするのか、初めに決める必要があります。 処理風量の決定要素1.捕集量2.取り出し方法(動力・人力) 3.取り出し周期 4.運搬方法 5.処理方法(再使用・廃棄) 6.運搬先(保管・廃棄場所) |
| 4 フード設計 |
処理風量はフードの設計で決まる粉塵の種類と発生状況及びフードの条件によって、風速を決定します。次に発生源の作業状態によってフードの形状と寸法が決定し、その後、吸込風量が決定されます。 集塵装置の処理風量の決定要素1.粉塵性状と発生状況2.フードの設計(形状・寸法・作業性) 3.制御風速(フードの形式と取付位置) 4.経済性(処理風量・圧力損失・ 装置の規模等との相互関係) |
| 5 排気温度の決定 |
排気温度をどの位にするか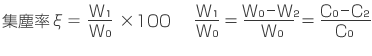 集塵率は上式により算出しますが一般作業場の場合、排気孔の粉塵温度C₂が公害関係法規、 条例等によって決められていることもあります。 |
| 有害な物質を発生する工程、作業の再検討 |
| 工程または作業を改善して有害物質の発生を極力少なくします。 (作業工程の改善) |
| フード型式の決定 |
|
原則として発生源にできるだけ近づけて囲うようにするため、ブース型か囲い型かを考えます。
それがフードの形状によって作業上不可能な場合は、 側方型などを検討します。 また、できるだけ風量が少ないスロット型やテーブル上フード等を考えます。 |
| フード設置位置及び排気の方向の決定 |
|
発生機構より発散方向、飛散速度、熱散限界を考慮し、 飛散方向にこれを受けるようなフード開口面を置きます。
フードが側方型や天蓋型等の場合は発生源とフード開口面との間に作業者が入らないようにし、 空気より重いガス等は下方で吸引します。 |
| 開口面周囲状態の決定 |
|
開口面の周囲が全く自由に開いているより、 一側面でも閉塞されている方が排気効果は著しく大きくなります。
従って、作業に差しつかえない程度に周囲を囲み、 有害物制御に役立たない空気を吸い込まないようにします。 |
| フード型まわりの乱れ気流の防止 |
|
補捉点附近の乱れ気流が制御風速に対し、無視できない程度に大きい場合、
そのままでは、必要以上に大きな制御風速を与えなければならなくなります。 また、場合によってはフードの正常な機能を失う場合もあります。 |
| プッシュプル方向 |
|
噴流の力を利用して汚染ガスを排出することができます。
この場合、吸込気流だけで排出する処理風量に比べてずっと少ないというメリットがあります。 |
| 制御風速の決定 |
|
有害物質の飛散限界の最も遠い点よりフード開口内に流入させるために必要な
最小の風速を制御風速といい、フード型式や取付位置より決定します。
また制御風速は処理風量を決定する重要な要因になります。 |